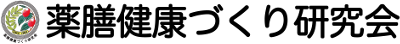役に立つ身近な 食品・生薬
【枇杷葉】 別名 生枇杷 炙枇杷
| (名称) | びわの葉 |
| (所属) | バラ科 |
| (由来) |
諸説ありますが葉も果実も楽器の琵琶の形に似ているからという説があります |
| (産地) |
日本の各県 原産地は中国で花、種、根まで全樹を薬用に用いています |
| (性味/帰経) | 微寒・苦 / 肺胃 |
| (働き) | 消炎・排膿、鎮吐などの作用があり、方剤では辛夷清肺湯、甘露飲に配合されています (ほてりやすい人、乾燥による咳、しゃっくり、吐き気、食欲不振、暑気あたり、疲労回復などに) |
| (常用量) | 6g から15g |
| (応用) | 江戸時代には夏の風物詩として、枇杷の葉を使った「枇杷葉湯」が好まれていました |
| (採取時期) | 晩春から初夏または9月 大きくて緑色で新しい葉が良い。影干しをします |
| (注意) | 喉に刺激を与えてしまうため、葉裏の産毛(毛茸モウジ)はタワシ等でしっかり洗い落とすこと |
(文献) 薬膳素材辞典 暮らしの薬膳手帳 薬草・漢方薬 薬草カラー大辞典
利用法
びわの葉エキス(外用薬)
- びわの葉(硬め) 30~40枚
- ホワイトリカー 2カップ
①表と裏をしっかり洗った葉を細かく刻みホワイトリカーと一緒に広口瓶に入れ2~4ヶ月ほど置き、漉してエキスを保存する。(関節炎、神経痛、リウマチ、打ち身、捻挫、打撲、皮膚炎、腫れ物などに)
びわの葉湯(飲物)
- びわの葉 20g
- 水 2カップ
- はちみつ 適宜
①表と裏をしっかり洗った葉を1㎝幅に切って鍋に入れ、水を加えて加熱し、沸騰したら弱火にして半量まで煎じる。お好みではちみつを加えて飲む。
(咳や痰の風邪、百日咳、気管支炎、気管支喘息などに)